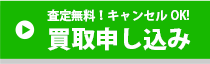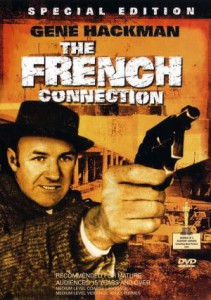フレンチ・コネクション/映画あらすじ・レビュー(ジーン・ハックマン、ロイ・シャイダー、ウィリアム・フリードキン監督の骨太男汁映画)
フレンチ・コネクション あらすじ
ニューヨーク市警察麻薬課の刑事ドイルとルソーは、売人逮捕のあと気晴らしで訪れたナイトクラブで気になるグループを見かける。
それはマフィアの組長たちと、やけに金払いのいい若い夫婦。
その後、彼らは若い夫婦を監視するが、その動きはまさしく何か犯罪の影を匂わせていた。
やがて、大きな麻薬がらみの取引があると確信した2人は、周囲を巻き込み執念の捜査を開始する。
フレンチ・コネクション レビュー
数々の賞を獲得し、ジーン・ハックマンとロイ・シャイダーの存在感を不動のものにしたこの作品は、間違いなく男臭さがバッチリ匂う骨太男汁映画だ。
なんだか凄くいい出汁がとれそうだが、決して可愛い娘がシャレオツなお店を紹介する情報番組よろしく「え~すごい出汁がきいてる~!それになんかぁ~まろやかでぇ~おいしい~」と味わいながら食べられるものじゃない。
「バカヤロー!味にまろやかさなんて要るかッ!」と怒鳴られながら食べる激辛濃厚激熱ラーメンのようなもので、容赦なく男のムチで痛めつけられるのだ。
なんだか自分で書いていて、何のことを書いているのかわからなくなってしまったが、それほど、この映画は男臭い。
つまりそういうことなのだ。(最初からそう書け)
監督は「エクソシスト(1973)」「L.A.大捜査線/狼たちの街(1985)」のウィリアム・フリードキン。
本来は映画のなかで描かれる男臭さは大好物だが、時に私の許容範囲を超えてしまうのがこの監督の作品。
女性が求めるような「男臭くて強引だが温かみのある男」の演出は一切省かれている。
「L.A.大捜査線/狼たちの街(1985)」を観たときもそう思ったが、女性に対する視線に堂々たる男尊女卑を感じるのだ。
ただ、決して誤解しないでほしいが私にフェミニズム思考はないし、男が強くあり女が男を立てる世界観は嫌いじゃない。
いわゆる女に媚びない男臭さ、そんな感じだと表現するのが適切だろうか。
また、主演の刑事2人にはエドワード・イーガン刑事とサルヴァトーレ・グロッソ刑事という実在のモデルがいる。
映画のなかでも上司や同僚としてカメオ出演し、元刑事としてアドバイザーになったようだ。
おまけに、この映画のあとは2人とも映画やテレビ業界に入ったとのこと。
そして、この作品自体が先述した実在の刑事2人によって、フランスから密輸された麻薬を押収した事件(ノンフィクション小説)をモデルにしている。
それゆえに、要所要所リアル感に満ちているのがこの映画の大きな特徴だ。
延々と続く追跡と張り込みや、刑事と情報屋がお互いの立場を守りながら会話の場を設けるため一芝居を打つところ。
また、ただただ物的証拠を求めて車を解体していくところなどだ。
また、アドバイザーとなったエドワード・イーガンとサルヴァトーレ・グロッソが経験したであろう数々の苦労が作品のなかで表現されている。
グルメで身なりのいい悪党が高級なレストランでばっちりフルコースを味わっている最中、正義というよりは「執念」だけに突き動かされている刑事が、極寒のなか外で張り込んでいるところ。
「ちょっと、ちょっと!ドイル刑事ったらバッチリ悪党の視界に入っちゃっているんじゃないかしら」という観客の心配をよそに、震えながら外で飲み食いし(トイレはどうしたか知らないが)とにかく男臭く延々と張り込んでいるのだ。
刑事さんは本当に理不尽だろうなと、心から思ったシーンでもある。
あと、どうでもいいのだが…途中、なんか人が(ほとんど死んでいるんじゃないかと思うような状態で)倒れていたが、ドイル刑事は完全に無視していた。
どうやら自分が追っているヤマ以外はまったく興味がないらしい。
いずれにせよ、倒れている人は無視して物語はハードボイルドに進んでいく。
また、突っ込み連発で申し訳ないが、やはり捨て置けないのは、最初に登場したときは“すご腕の殺し屋”風だった男が、ジーン・ハックマン演じるドイル刑事を消そうとしたとき、あまりにもスナイパーとしての腕が低すぎたこと。
どんだけ外しまくってるんじゃと思わず突っ込みを入れた次第だ。
グルメな洒落こきフランス人悪党の、気取って尚且つ“いけしゃあしゃあ”としながらドイル刑事の尾行をまくシーンはなかなか面白かっただけに、殺し屋のダメっぷりにはズッコケた。
まあしかし、現実の世界では完全無欠の人間なんていないし、むしろ現代の映画で描かれる「デキ過ぎる殺し屋」の方がもはやファンタジーなのかもしれない。
そういった意味でも、この映画のリアリティは半端ない。
しかし…
犯人をつかまえるためには手段を選ばない、ちょっぴり女好きなドイル刑事は、「止まれ!警察だ!犯人を追っている!」と一般市民の車を借りたはいいが、完全にカーチェイスでグッチャグチャにしてしまうし、ラストシーンはあまりにも不注意すぎる。
いっ…いやいや、実際に犯行現場へ突入して銃撃戦になったら、誰もが危険なのだから、やはりこれも現実味を帯びた演出なのだろう。
だが、この不注意で私の気持ちは完全に置いてかれてしまい、最後のエピローグ的なものが頭に入ってこなかった。
それもこれも、もはや正義ではなく、男の「執念」そのものを描くためなのかもしれない。
ロイ・シャイダーは、実在のモデルであるソニー・グロッソ刑事が持つ“陰気な雰囲気”にピッタリだからとこの役柄に決まったらしいが、そこで激しく同情してしまう。
何故って、もし自分の相棒があんな感じであれば暗い表情になること請け合いだし。
ドイル(実在した人物はエドワード・イーガン)は刑事としての腕は確かかも知れないが、もはやそのハチャメチャぶりは激怒した超人ハルク並みだ。
ジーン・ハックマンもロイ・シャイダーも好きな俳優さんだし、刑事の張り込みシーンも、追跡シーンにも臨場感があり、銃撃戦もリアリティがあって迫力がある。
廃墟の不気味な演出も良かった。
しかし、あんなに抜かりないはずのグルメな洒落こきフランス人悪党が、最後の最後に「つけられてはいないので大丈夫だと思うが」ってやたら不注意おじさんに変身してしまったのは何故なのだ―ッ。
と、数々の突っ込みを入れながら、ハードボイルドにこの映画を観終えたのであった…。
「完」
映画と現実の狭間でROCKするライター中山陽子(gatto)でした。
フレンチ・コネクション(1971)
監督 ウィリアム・フリードキン
出演 ジーン・ハックマン/ロイ・シャイダー/フェルナンド・レイ/トニー・ロー・ビアンコ
ウィリアム・フリードキン監督作品の買取金額の相場はこちら
ジーン・ハックマン出演作品の買取金額の相場はこちら
ロイ・シャイダー出演作品の買取金額の相場はこちら