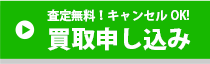今日の1本 紅の豚 (1992) 岸豊のレビュー
ジブリ作品における男の主人公といえば、『天空の城ラピュタ』(1986)のパズーや、『もののけ姫』(1997)のアシタカ、『ハウルの動く城』(2004)のハウルなど、まあイケメンぞろいである。それに対して本作のポルコは豚顔で中年、しかも社会的には犯罪者と、ジブリの主人公像から完全に逸脱した稀有なキャラクターだ。しかし、そんなポルコだからこそ出せる哀愁がたまらなくかっこいい。豚顔なのにモテモテ、キザなセリフや振る舞いが成立してしまうのも痺れる。
ヒロインのフィオに関しては、彼女ほど宮崎駿の理想を詰め込んだヒロインはいない。容姿端麗で航空力学の専門的な知識を持ち、飛行艇の設計も超一流の彼女は、時にはポルコに有無を言わさぬ、ジブリのヒロインらしい強い意思を持った女性でもある。フィオとポルコの関係においては、フィオの目線からはポルコへの恋愛感情が、ポルコの目線からは父性が感じられる。この関係性は、殺し屋と少女が織り成す暴力的な純愛を描いた名作『レオン』(1994)に近いものを感じさせる。
ポルコの首を狙うマンマユート団などの空賊は、拝金主義者でありながらも、ジブリ作品らしい憎めないキャラクターとしていい味を出している。
ポルコのライバルであり、フィオを懸けて勝負するカーチスも、20世紀初頭の田舎から出てきたアメリカ人を象徴するような、夢見がちな愛すべき男としてストーリーを大いに盛り上げる。こうしてキャラクターを整理すると、本作は物語に深く関わる必要悪を敢えて排除した珍しいジブリ作品でもあることが分かる。
そんな本作の舞台は世界恐慌下のアドリア海だ。ミラノではポルコを尾行するスパイの活動が描かれているように、当時のイタリアはムッソリーニのファシズム政権下でもあり、共産主義による社会的な弾圧が厳しかった。そんな息苦しい地上から飛び立ち、青い空を自由に飛びまわる飛空挺乗りの男たちは最高にかっこいい。彼らは貧乏でも自由と冒険心にあふれた、気持ちの良い男たちだ。
大空を飛び回る迫力の戦闘シーンだけでなく、フィオが虫に息を吐いて飛ばすシーンは、風俗画のように、さりげない一瞬を切り取っているのも味わい深い。
ポルコがなぜ豚になってしまったのかが語られるシーンも素晴らしい。戦争での臨死体験と仲間たちを救うことができなかったことへの悔恨が語られるこのシーンは、ランプの灯りによるキアロスクーロ(明暗法)によってコントラストが効いており、まるでジョルジュ=ドゥ・ラトゥールの絵画のように美しい画面構成となっている。
そしてエンディングでは、ジーナを演じた加藤登紀子が歌う「時には昔の話を」が言いようのないノスタルジーをかきたてながら、物語の幕は閉じる。
自由を求め続け、空に生きた男たちの生きざまは、本作のキャッチコピーである、「かっこいいとは、こういうことさ」そのものだった。何度観ても色褪せない名作だ。
紅の豚
監督: 宮崎駿
DVD・CD・ゲーム何でも高価買取します!
スピート宅配買取バリQ