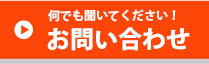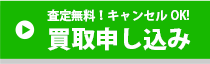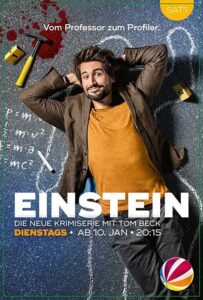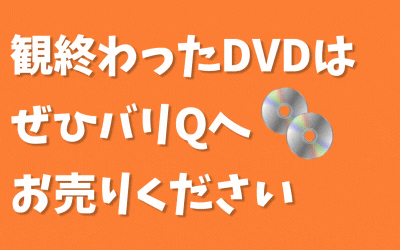【アインシュタイン ~天才科学者の殺人捜査~】
科学捜査好きならおすすめ。アインシュタインの子孫が事件を解決するドイツ発ドラマ※ネタバレあり
物理学が人々を救う。実験室ではなく現場で。
【あらすじ】
最初はお互いに「事件解決のため」「逮捕されないため」とイヤイヤながら協力していたが――やがて彼らには友情と愛情? らしきものが生まれていく。
じつはこのフェリックス、あのアルベルト・アインシュタインの子孫。
態度がデカくて傲慢で、奇抜な言動が周囲を辟易させることも多いが、そのずば抜けた頭脳はしっかりと受け継がれていた。教壇に立ち、捜査に協力する傍ら、人類史に残る偉大な発明も成し遂げていたのだ。
しかし、父親と同じ治療薬のない難病にかかっている彼には、あまり時間が残されていなかった。しかも、彼の発明には怪しい組織や人物が次々と近寄ってくる。
果たして、フェリックスと警察チームの運命やいかに……!?
天才で薬物と女が大好きな憎めないクズキャラが謎を解き明かします
【レビュー】※ネタバレします!
● クズキャラが「いい人」に見えてくる、いつものアレ
この作品は、ドイツ発の1話完結型スッキリほんわか系犯罪捜査ドラマです。主人公のフェリックス・ヴィンターベルク(通称アインシュタイン)が終盤、まるで一休さんのようにひらめいて、スルスルッと事件を解決していきます。
一休さんと違うのは(誰も似ているとは言っていませんが)、その際にたくさんの数式や図形が頭に浮かぶこと。極めて高い知能と物理学の専門知識を武器に、次々と事件を解決していきます。
ただ難点は、彼がひどく自己中心的で、傲慢で、女と薬物には目がないこと。そういった部分が警察チームにも筆者にも、最初は嫌悪されたのです。
でーもー、
そこはお約束。
苦難を共にしていくなかで、警察チームとは徐々に信頼と友情と愛情らしきものを積み重ねていきます。筆者にとっても好きなキャラクターのひとりになりました。
最初はどこから見てもクズだったフェリックスが、「いい奴にしか見えなくなってくる」のも、こうしたキャラクターが活躍するドラマのおもしろさかもしれません。
そして、何と言っても科学的側面のおもしろさが、このドラマにはあるのです。
● 科学的な視点ではリアル半分・ファンタジー半分?:逆位相
あるエピソードを取り上げてみましょう。
シーズン3の第9話「逆位相」は、天才フェリックスと天才ヒットマンの知能戦が描かれ、特におもしろい回でした。
物語の始まりは、警察チームがマフィア裁判の重要証人を、警察署内にかくまうところから。厳重な警備体制で証人を保護していたはずでしたが、密室のなかで証人のひとりがヒットマンに殺されてしまいます。
そこでフェリックス登場。
現場をチョロチョロっと見て、すぐに「毒殺」だと見抜きます。ヒットマンが証人のいる部屋の外壁に穴を開け、そこから毒ガスを注入したのです。
「そんなアホな! すごい騒音がするからすぐ誰かが気づくだろぃ!」という警察チームにフェリックスは、
こんなふうに謎を解いてあげました。
振動板を壁につけて、ドリルの音と同じ周波数で逆位相音を壁に発生させ、ドリルの音を打ち消したのさ~。
これは確かに……、物理学的観点で正しいアプローチかもしれません。
音波(空気の振動)に対し、まったく同じ周波数・振幅で「位相が180度ずれた波」をぶつけると、音が打ち消し合う、つまり「無音」に近づくというやつ。
ノイズキャンセリングヘッドホンで使われている技術と同じ理屈。
でも~~~。
音響工学、精密工学、物理学――複数の技術を組み合わせた高度なトリック。超頭脳派ヒットマンでなければ到底できない芸当です。
🤔ホンマかいな。
まあ、「アインシュタインの子孫」と渡り合うには、これくらい緻密で大胆(=あり得ないレベルの高度さ)な仕掛けが必要だったのかもしれませんね。
● 科学的な視点ではリアル半分・ファンタジー半分?:サイホン式トイレ
で、じつはその証人はふたり。ひとり生き残っていました。その証人が「この警察署ぜーんぜん安全じゃねーぞ」と逃げ出し、偶然居合わせたフェリックスに安全な場所に連れて行けと、おねだりしたのです(銃で脅してね)。
結果、なぜか防弾扉だという、大学構内にあるフェリックスのお家へ。
大学はお休み期間でほとんど人がいない状況です。
しかし、敵(超頭脳派ヒットマン)もさる者、扉の前に立ち話しかけ、そのあいだに窓から逃げようとする人間を、向かいのビルに設置したカメラを利用して、手元のタブレットで確認し、タブレット操作により銃で狙い撃ちするのでした。(しゅごい)
そのため、フェリックスと証人は動けない状態に。そこでヒットマンは最初の証人を殺したように、今度は逆位相を使わず天井に穴を開け、毒ガスを注入しようとしたのです。
追い込まれたフェリックスは考えました。
で、ピーン!💡
(※人間の脳のイメージ。MRI画像のお腹の部分っぽいですが……😅)
サイホン作用を利用して汚物を排出するタイプですよね。で、そのトイレの管の曲がりくねった部分には、下水の空気が室内に上がってこないように水が満ちています。それがつまり、封水(トラップ)。
フェリックスはこの封水にホースを差し込めば、その向こう側=下水の空気にたどり着けると考えたわけです。
そして、その際には鼻呼吸しないよう鼻を洗濯バサミで閉じ、証人と交互にホースから息を吸い、その場で吐いていました。下水に吐くと酸素じゃなくCO₂で満たされる危険性があるからです。
そうしているうちに無事、毒ガスも無効化。穴から「死んだかな?」と覗いたヒットマンの目を細い棒で突き、「まだ、生きてるぞ!バーロー!」的なことを言っていました。
つまり、
作戦は見事大成功!
ですが!
現実的には下水の空気なんて吸ったら、硫化水素中毒で命を落としてしまうかもしれません。
毒ガスから逃れるために下水の空気を吸うなんて、それってつまり――
「火を避けるためにドライアイスが大量に入ったボックスに逃げ込んだら凍傷になった」みたいな状況なんです。
絶対にまねはしないでください!(しないか)
● 科学的な視点ではリアル半分・ファンタジー半分?:月の反射鏡
で、最後。
何度も九死に一生を得たフェリックスと証人ですが……、
まだ助かったわけではありません。なんせ、警察チームはフェリックスの自宅に証人がいて、いままさにヒットマンに殺されんとしていることを知らないわけですから。
そのなかで、証人の名前が「ルナ(ラテン語で月を意味する)」だと知ったフェリックスはあることを思いつきました💡
大学内にあるフェリックスの部屋には、なんと天体望遠鏡があるのです。それには照準用のレーザーがついています。
フェリックスは、その光線を月に向かって照射しようと考えました。
なぜなら、アポロ11号のアームストロング船長たちが月に降り立った際に反射装置を設置していたから。いまもなお、地球からその反射装置にレーザー光を照射し、反射光(光子)が戻ってくるまでの時間を測定することで、地球と月の距離を高い精度で求めているといいます。
で、フェリックスは、
と考えたのです。
そうすれば月の研究者が気づく➡友人の研究者に伝わる➡仲間の警察に伝わるから。
でもでも、でもね~~~~~
月までの距離約38万キロメートル。モールス信号のように「光の間隔や長さ」を読み取れますか~~~~???
そもそも、反射装置ってコーナーキューブですよね? 普通に反射したら角度的に地球には戻ってこないので、複数の面で反射し合うと元の場所に光が戻るというやつ。だったらなおさらモールス信号が読み取れるのはファンタジー。
が、
一応、ドラマのなかでは、ハッキリとモールス信号になって月から返ってきていました。
で、無事仲間の警察に伝わり、ふたりは救出。
まあまあまあ、でもでも、どれも現実にはかなり厳しいけれど、「ドラマ的伏線+科学ガジェット」の合わせ技としてはどれも最高におもしろい。
こうした楽しみ方ができるからこそ、サイエンス好き、科学捜査好きならおすすめです。まったく別の視点では、「へ~~~😲ドイツでは、こういう顔がモテるんだ……」という新たな発見もできるかも……!?
クセ強だけどクセになる。科学と人間ドラマが絶妙に交差する本作、ぜひ一度味わってみてください。
(ライターgatto)
アインシュタイン ~天才科学者の殺人捜査~(2017~2019)
出演者:トム・ベック , アニカ ・エルンスト , ロルフ・カニース , ヘイリー・ルイーズ・ジョーンズ