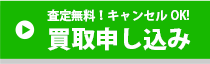今日の1本 イノセンス(2004) 岸豊のレビュー
前作『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』(1995)は、近未来SFの金字塔となり、『マトリックス』シリーズのウォシャウスキー姉弟をはじめとする世界中のクリエイターたちに影響を与えた。劇場版の2作目となる本作では、前作から4年後の西暦2032年を舞台に、少女型愛玩用「人造人間「ロクス・ソルス社製 Type2052 “ハダリ(HADALY)”」が起こした連続殺人事件について、お馴染み公安9課のバトーとトグサが捜査する姿を描く。
3DCGとセル画が混在した映像は、舞台の無国籍性や、映し出されるモチーフの数々に独特の雰囲気を与えている。川井憲次が手がけた音楽も素晴らしい。特に第2のメインテーマともいえる「傀儡謡」のコーラスは、総勢75人の民謡歌手の声が美しく調和した歌声で強烈なインパクトを与える。『ブレード・ランナー』を思い起こさせるデストピア的な街並みに合わせて流れるジャズも渋い。
本シリーズのモチーフとなっている「電脳化」は、もはや未来の話ではない。現に、Mind Transufer(精神転送)は、近い将来、それも数十年後には実用化されることが確実視されている。また、いずれ本作に登場するガイノイドのようなロボットも、現実世界に登場するだろう。彼らが実用化されれば、本作で描かれたようにセクサロイドとして、或いは少子化対策に使われる可能性は無きにしも非ずだ。
産業革命以降、人間は合理主義の追求としてロボットの研究を進めてきた。そして、人間は自らの手を煩わせることなく生活を営むことが合理的だと考えてきた。しかし、人間が自分の行動に責任を課さなくなれば、『ウォーリー』(2008)で描かれたように、人類の肉体と精神が退化していくのは明白だ。そうなったとき、人類は自分の過ちを認めることができるのだろうか?肉体を捨ててしまうのではないだろうか?人間は人間であり続けるため、つまり人類の繁栄のためにロボットを作ってきた、はずだった。しかし、ロボットが持つ完全性、つまり造形美や狂いのない思考といった人間が持たざるものに対する劣等感を抱いた結果、人間の中には本作におけるキムのように完全なロボットとなることを望む歪んだ精神が出現する可能性も大いに有り得る。今日の科学において、精神転送は「永遠の命」への鍵とされている。体が老朽化したら、新たな肉体に記憶をアップロードすれば、人間は生き続けることができるかもしれない。しかし、それが生命の正しい在り方なのだろうか。この疑問に対して、押井守は明確な回答を与えない。だからこそ、我々は真剣に考えていかなければならないのだ。人間であることとは、何なのか。そして我々がどうあるべきなのかを。
イノセンス
監督 押井守
バトーあなたがネットにアクセスする時、必ずここを見るのよ。
DVD宅配買取のバリQ